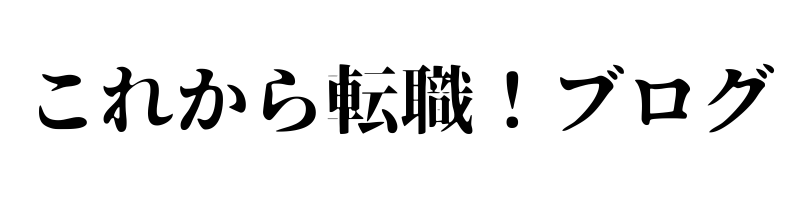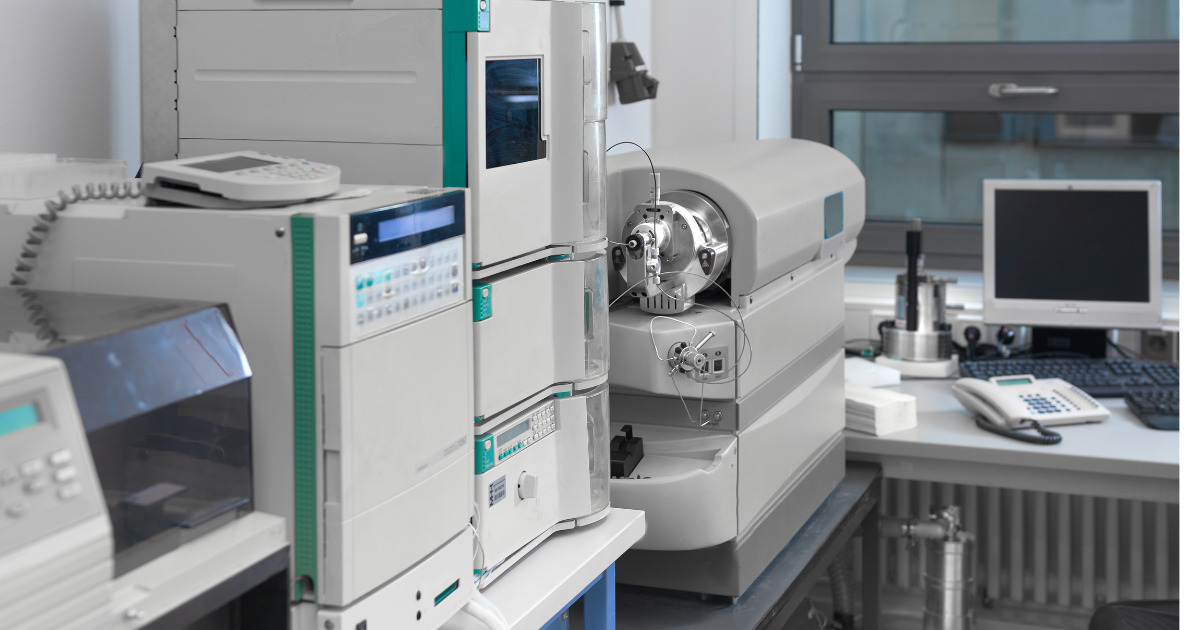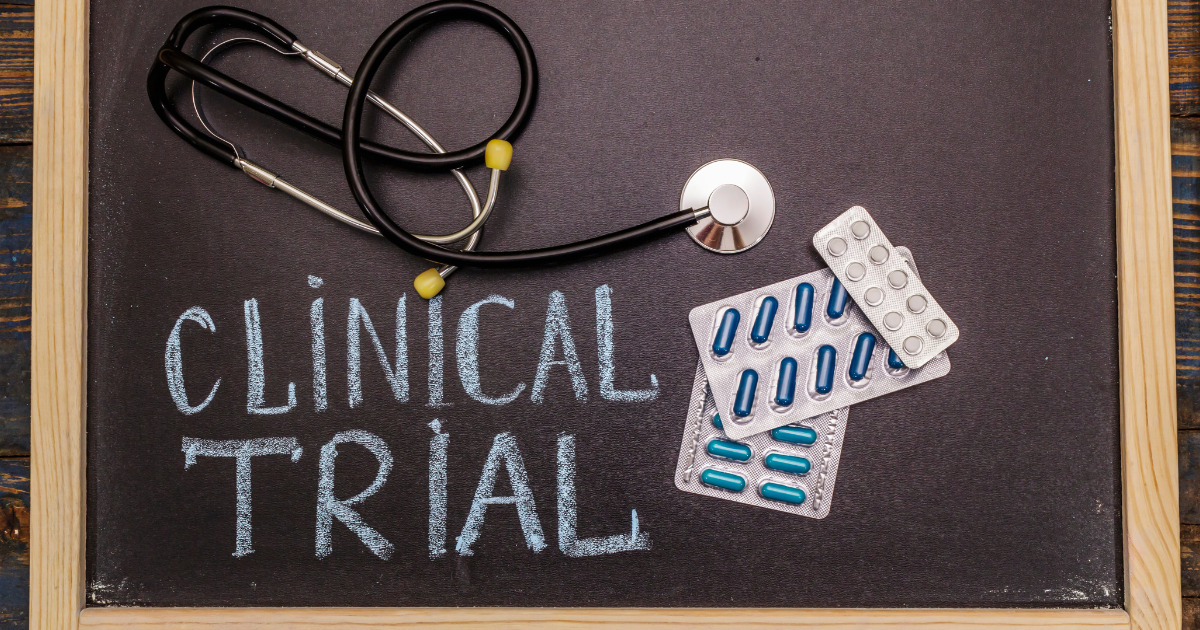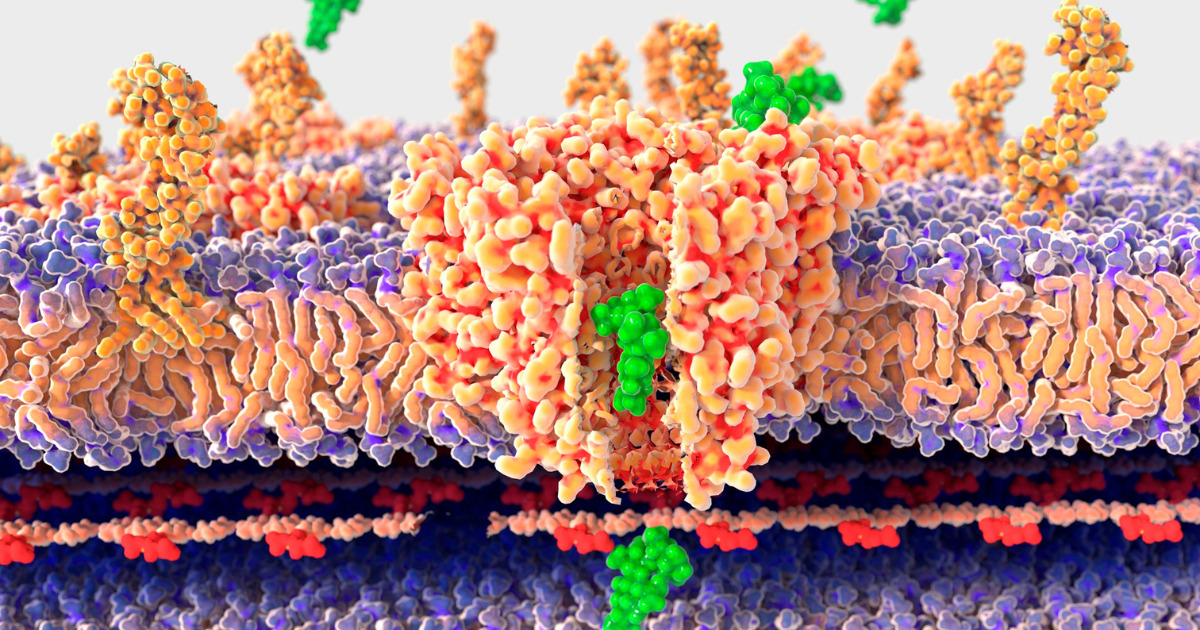薬学部や化学系、生物系の学部で大学院まで進学した方が、製薬企業に就職しようとする場合、研究部門を希望する方も多いでしょう。
これは大学院では皆が研究室に所属して研究をしているためです。
製薬企業の部署として研究部門を紹介します。
研究部門の中の各部署
研究部門の中には大学の研究室と同様に様々な部署があります。
代表的なものを紹介します。
合成部門
合成部門は研究部門の花形(人もお金も多い)の一つ。
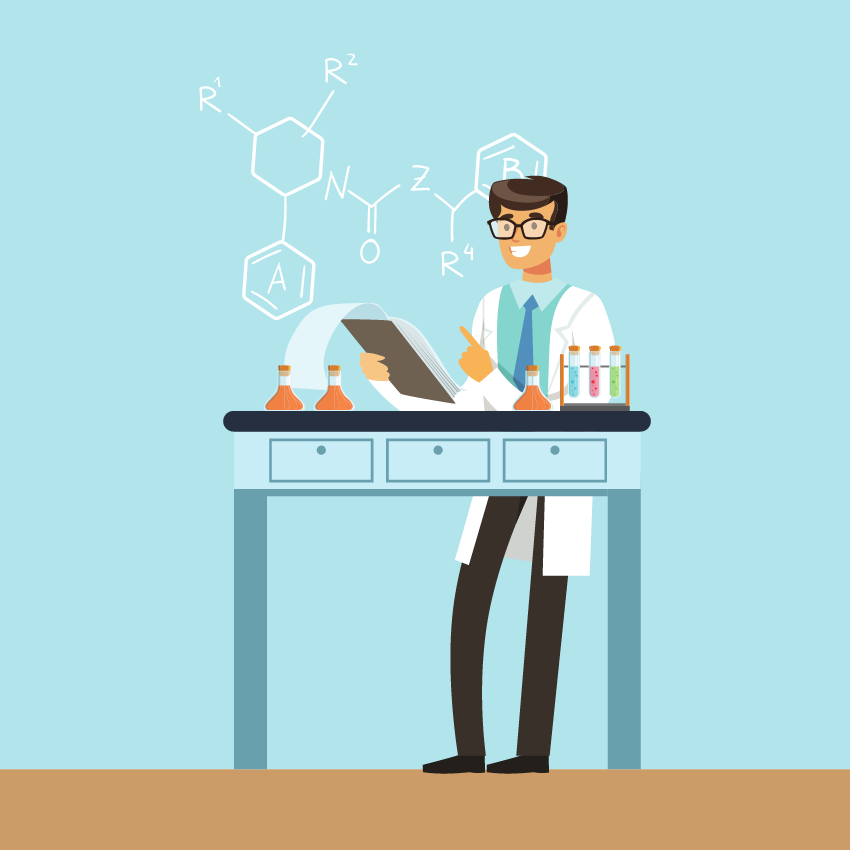
低分子の医薬品の設計、合成(化合物を製造する)が主な仕事です。
薬理部門と協力して目的とする標的(受容体など)に作用する化合物を合成します。
会社によっては中分子(ペプチドなど)も仕事の1つになります。
高分子の医薬品として使用されている抗体の製造は、低分子が専門の合成部門よりも、実験で抗体を多く使用する薬理部門が外部委託で実施することも多いです。
薬理部門
研究部門の花形(人もお金も多い)の一つ。
低分子の医薬品の場合、医薬品の作用として有望な目標(受容体など)を定め、HTS(ハイスループットスクリーニング、高速スクリーニング)にて化合物ライブラリーから有効な化合物候補を見つけます。
その化合物を合成部門と一緒に、一部を変更してさらに活性の高い化合物を得るようにします。
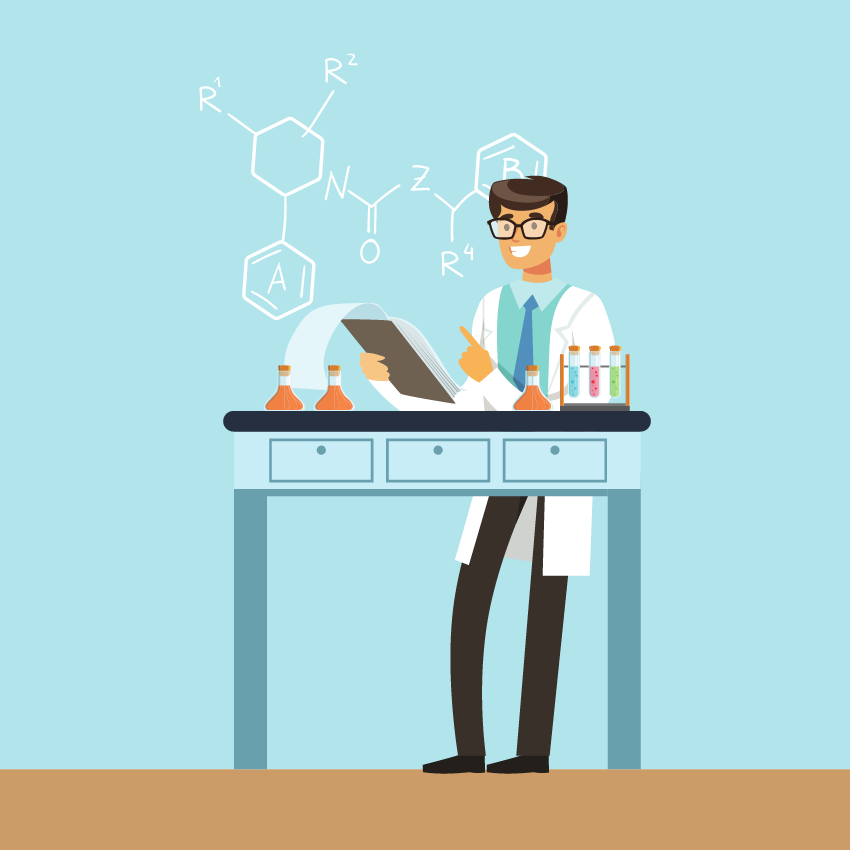
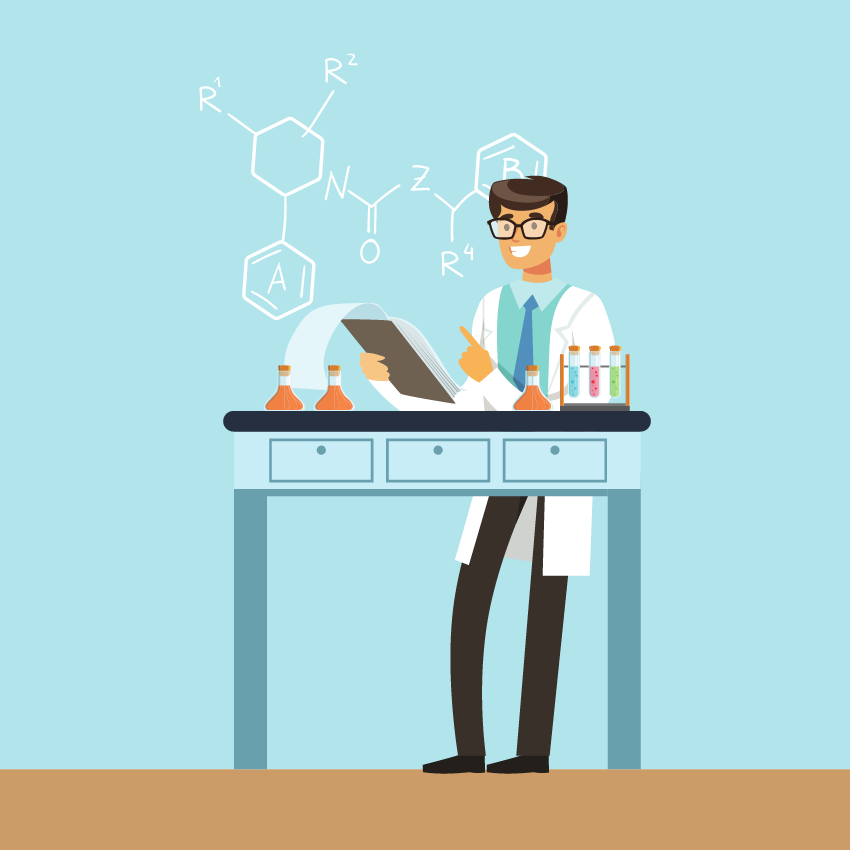
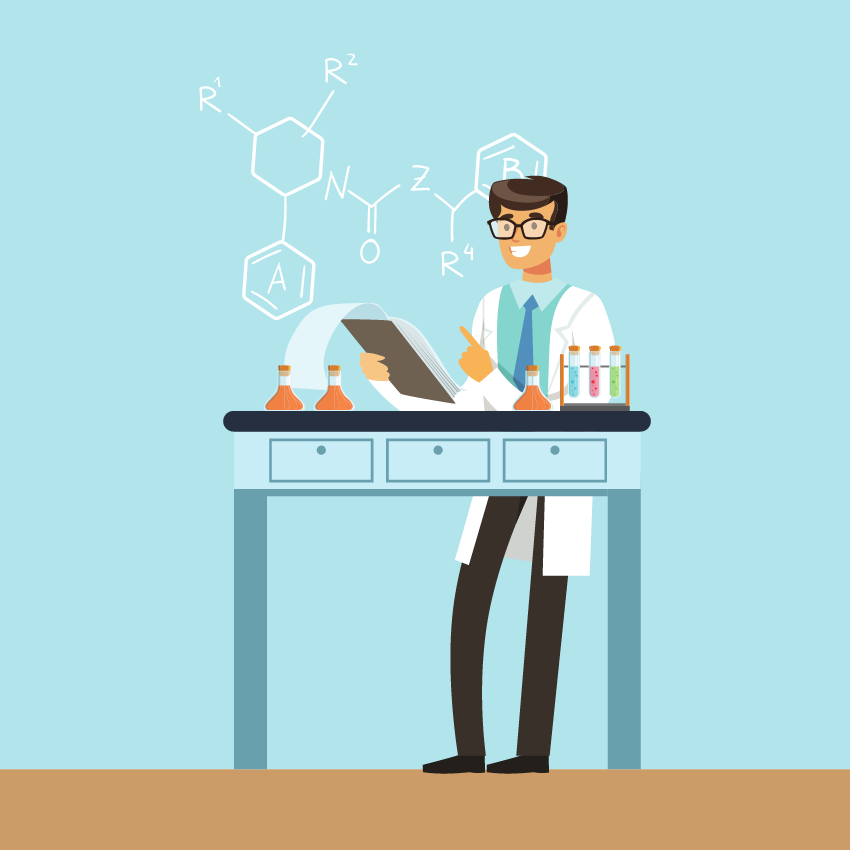
得られた化合物を動物に投与して遺伝子の活性を見るなど、大学の研究に最も近いことをしている部門です。
抗体を用いた医薬品の場合、薬理部門が外部委託で全権を持つこともあります。
分析部門
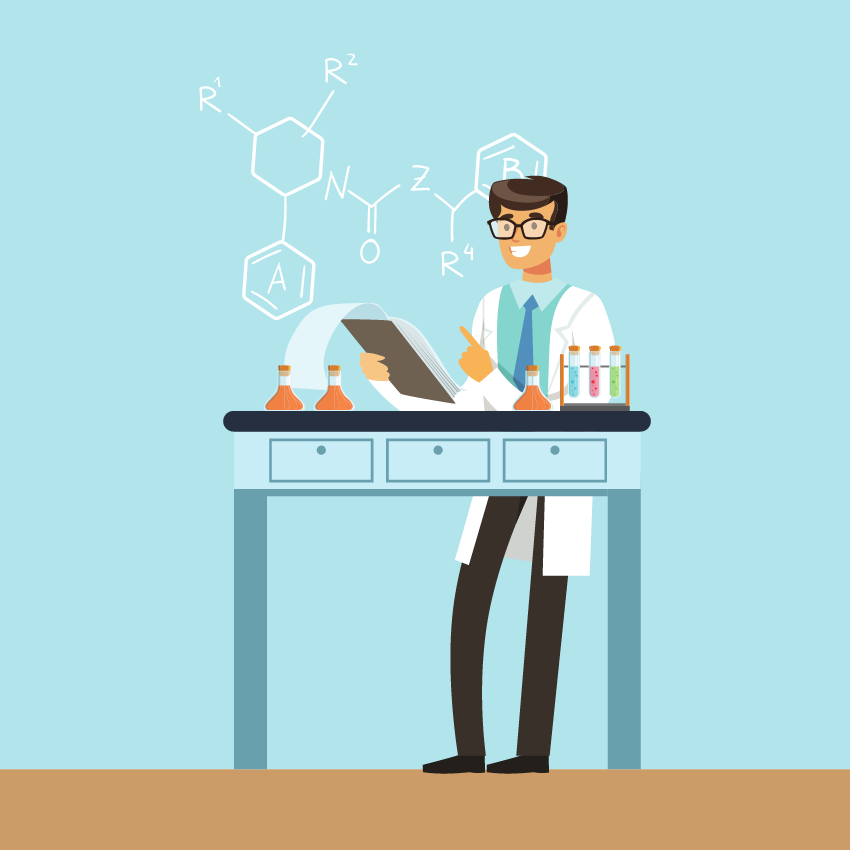
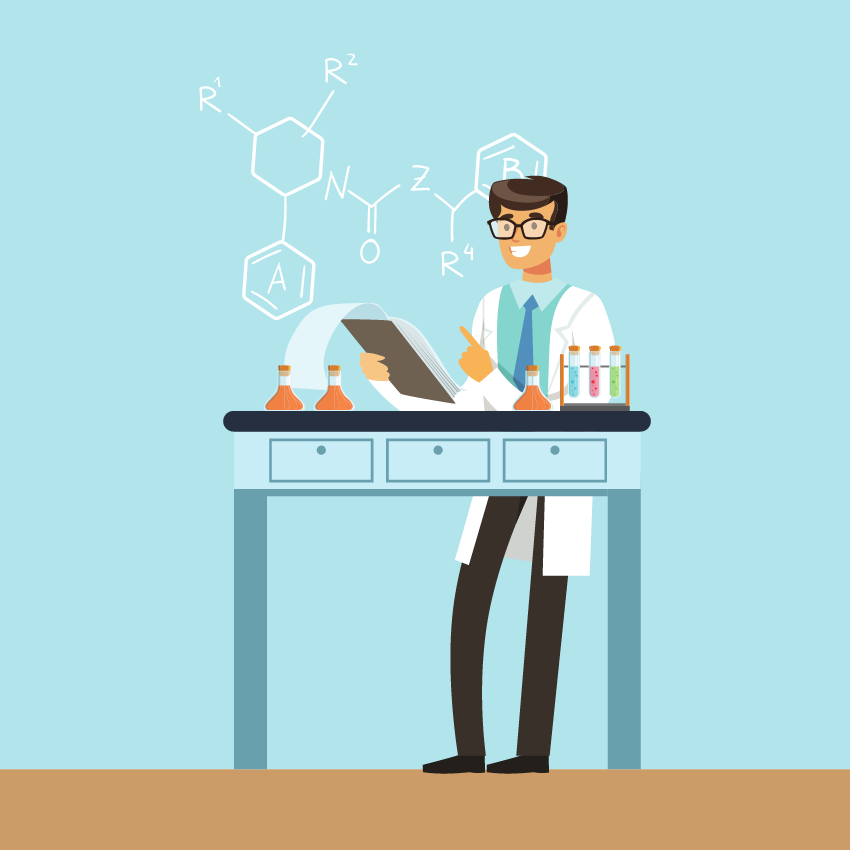
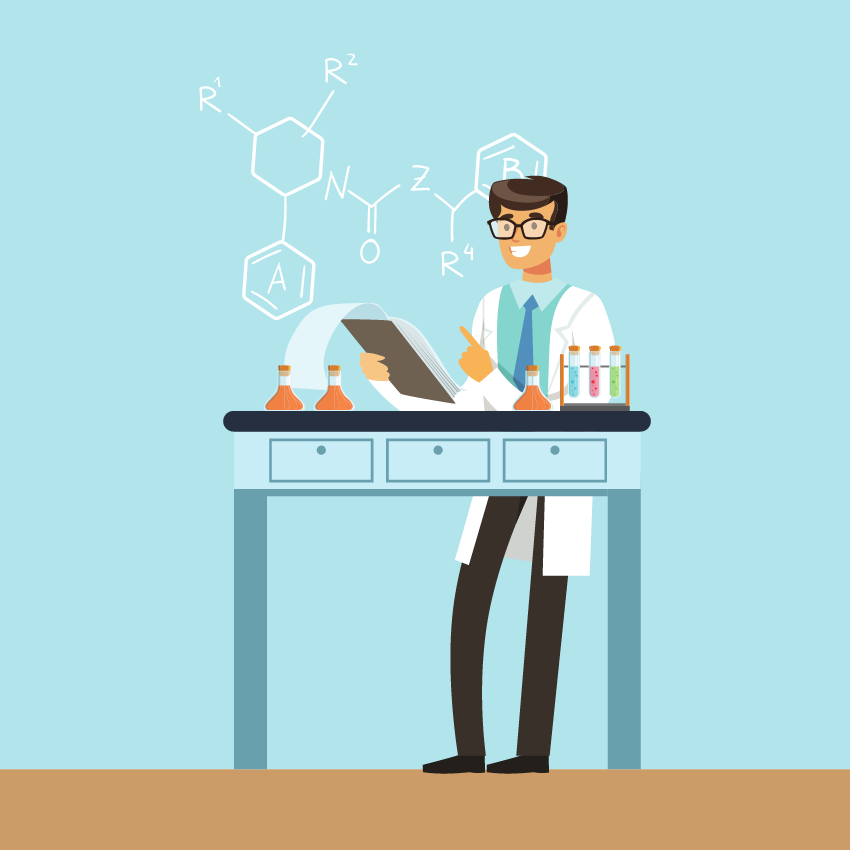
大学では地味なのに製薬企業では重要な部署といえば、分析部門といえます。
医薬品は低分子でも高分子でも正しい構造であること、化合物の安定性を確認するなど分析が必要なことが多く、業務は多岐に渡ります。
安全性部門
研究部門の中で動物を使用する部門といったら安全性部門です。
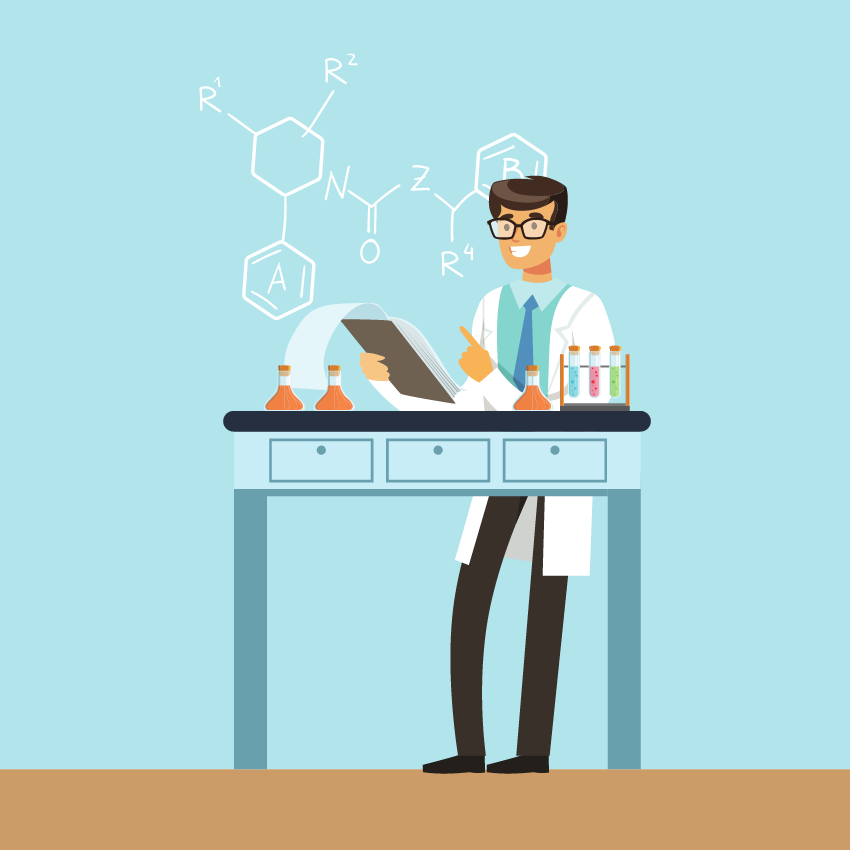
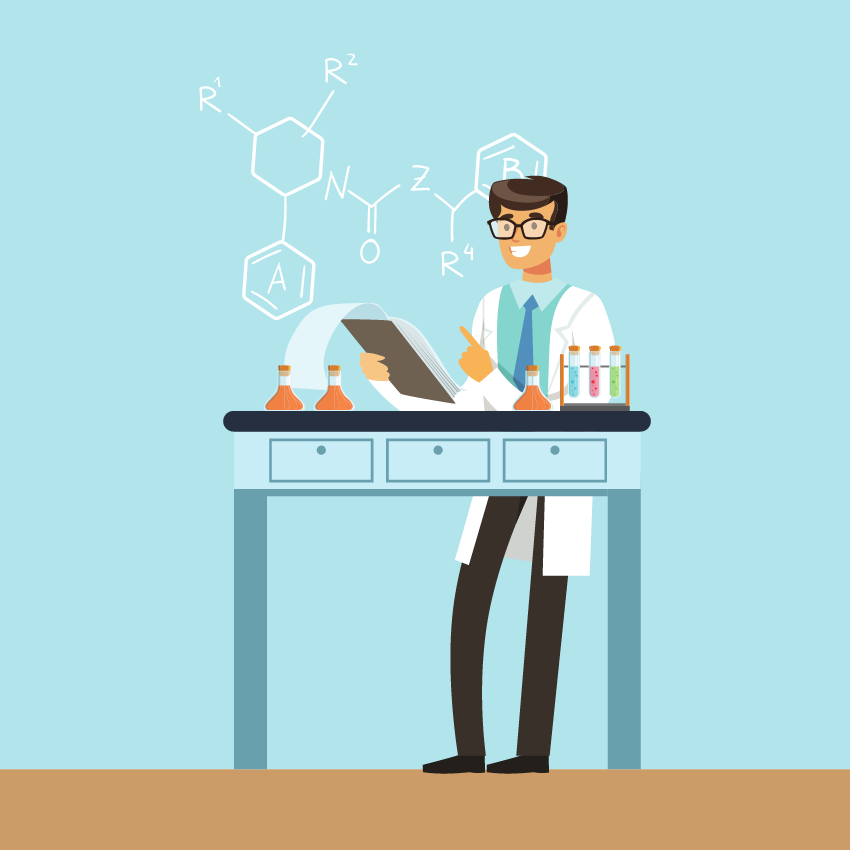
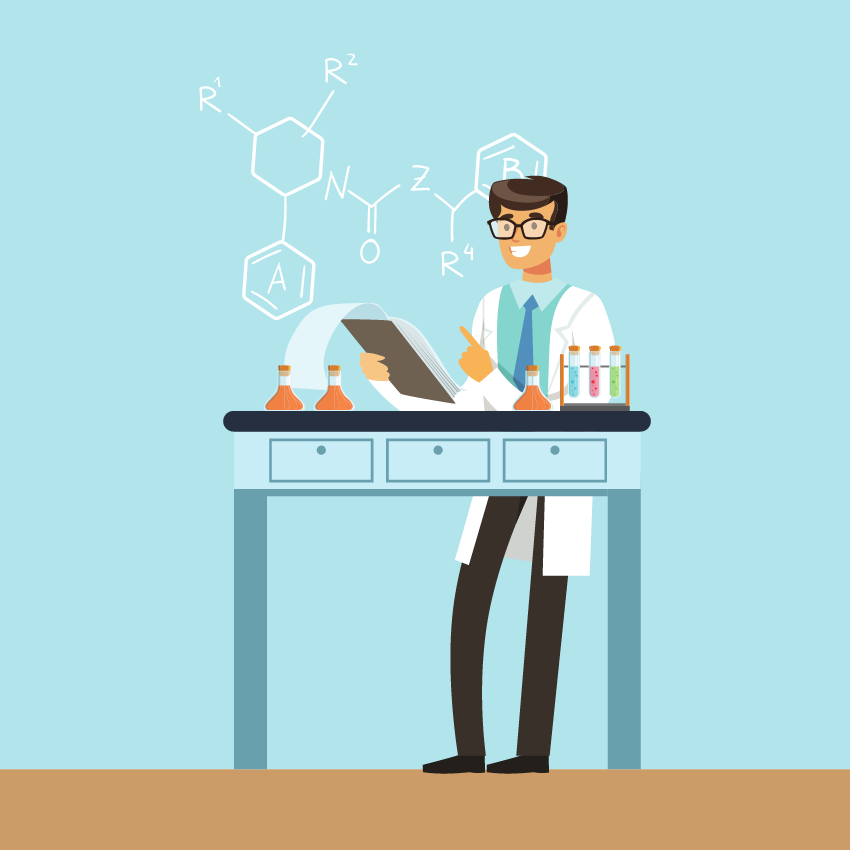
医薬品の安全性を、主に動物を用いて実験します。
安全性は医薬品開発の最重要事項といってもよいです。
そのためGLP(Good Laboratory Practice)といった世界的な厳しい規制の中で実験をする必要があります。
薬物動態部門
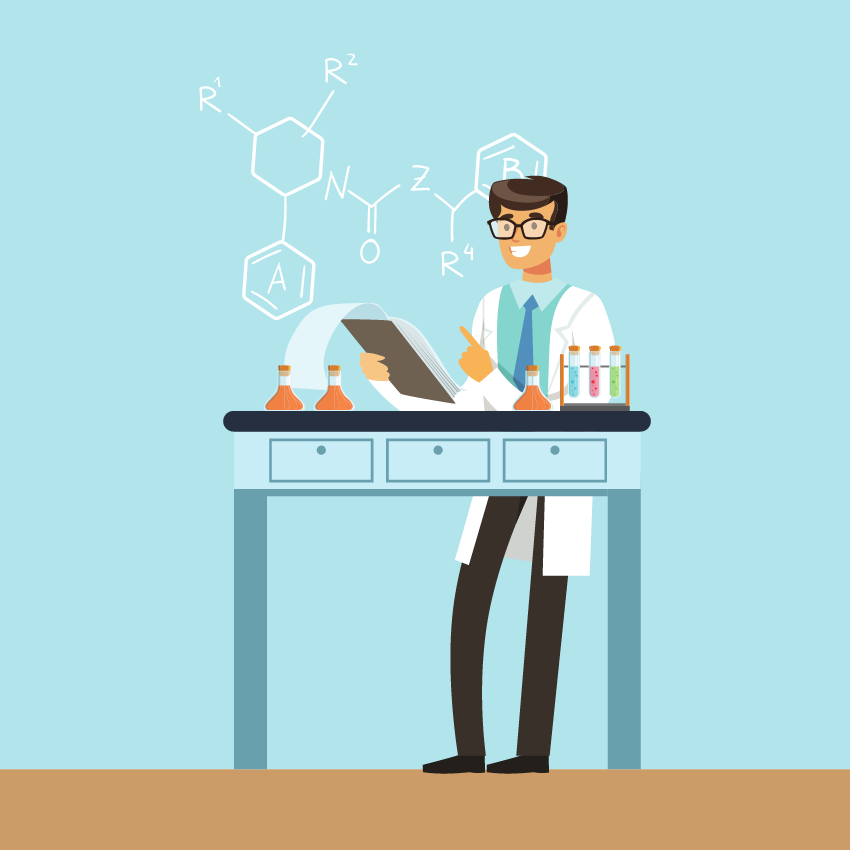
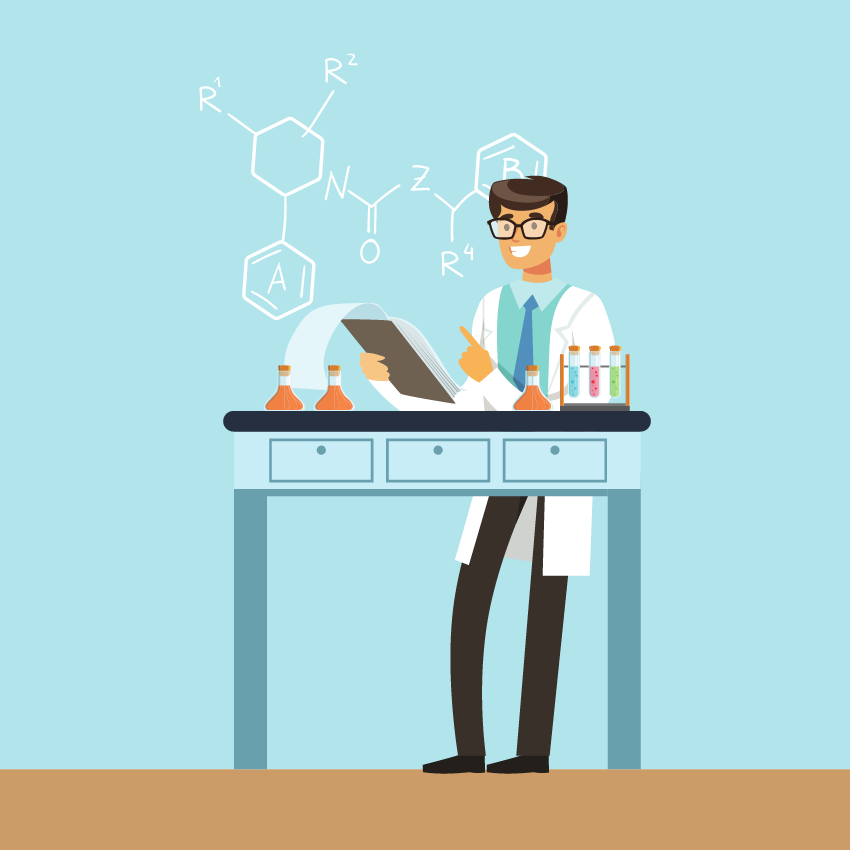
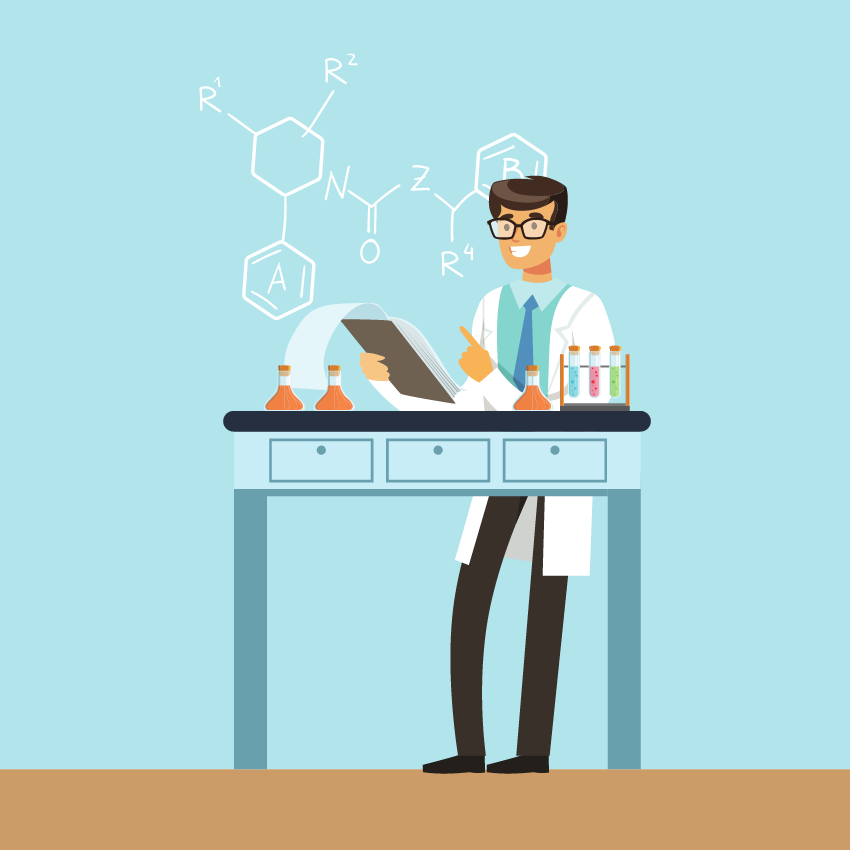
医薬品の体内での動き(肝臓に貯まる、腎臓から排出されるなど)を主に動物を用いて確認する部署です。
体内の医薬品はごく微量なのでLC/MS(液体クロマトグラフィー/質量分析)と呼ばれる高感度な機器を良く使用します。
医薬品の相互作用の確認、臨床での薬物濃度の測定など業務は多様です。
製剤部門
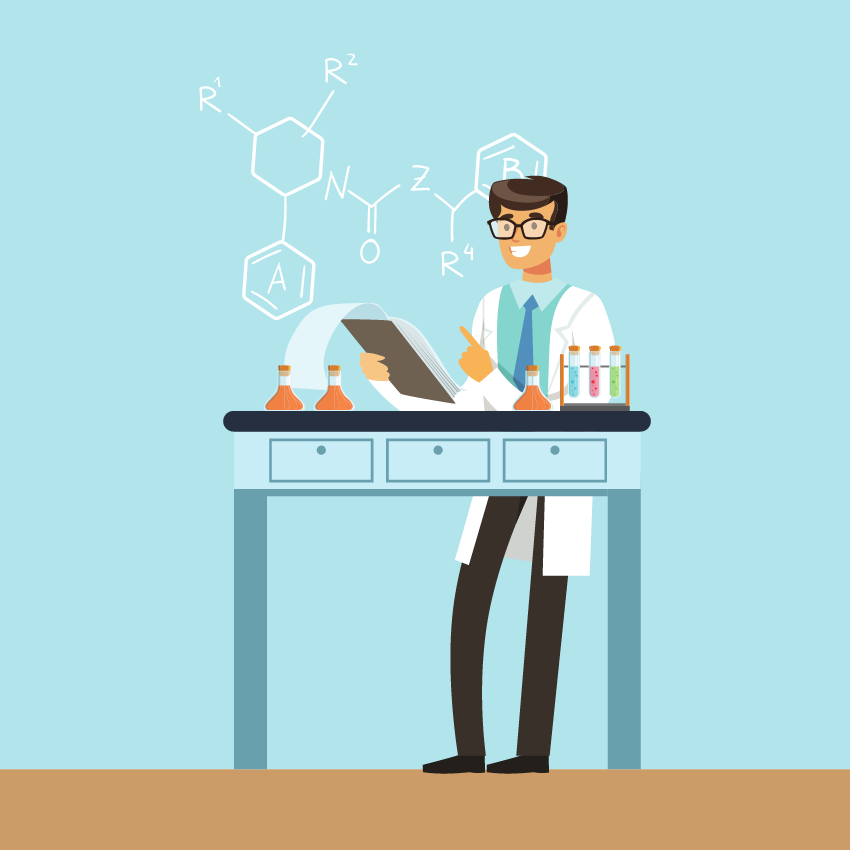
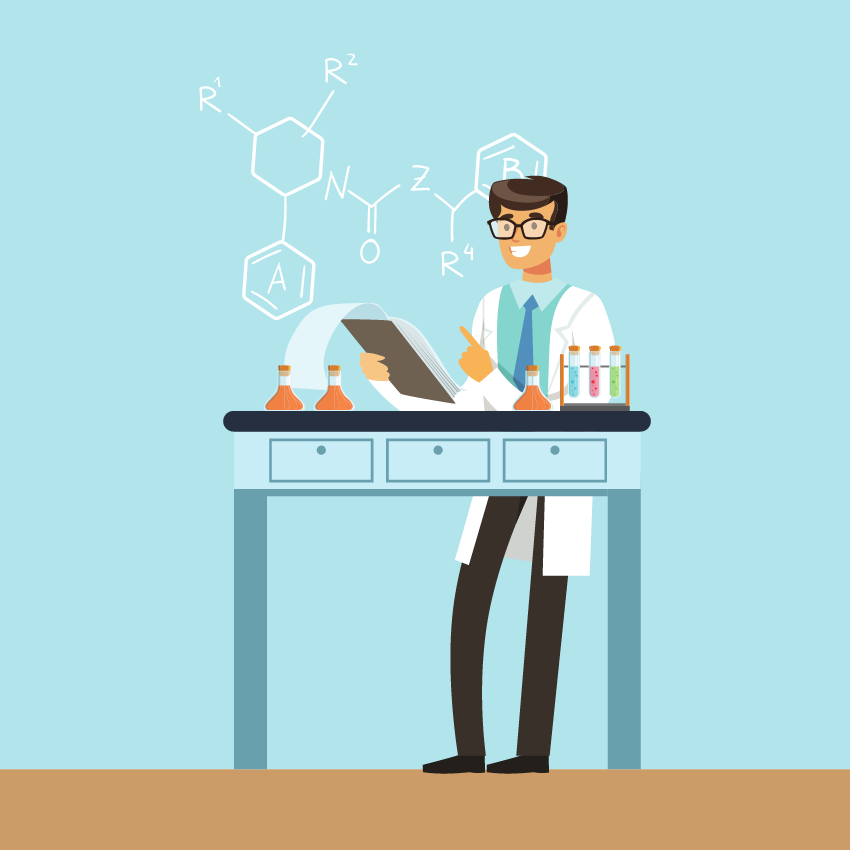
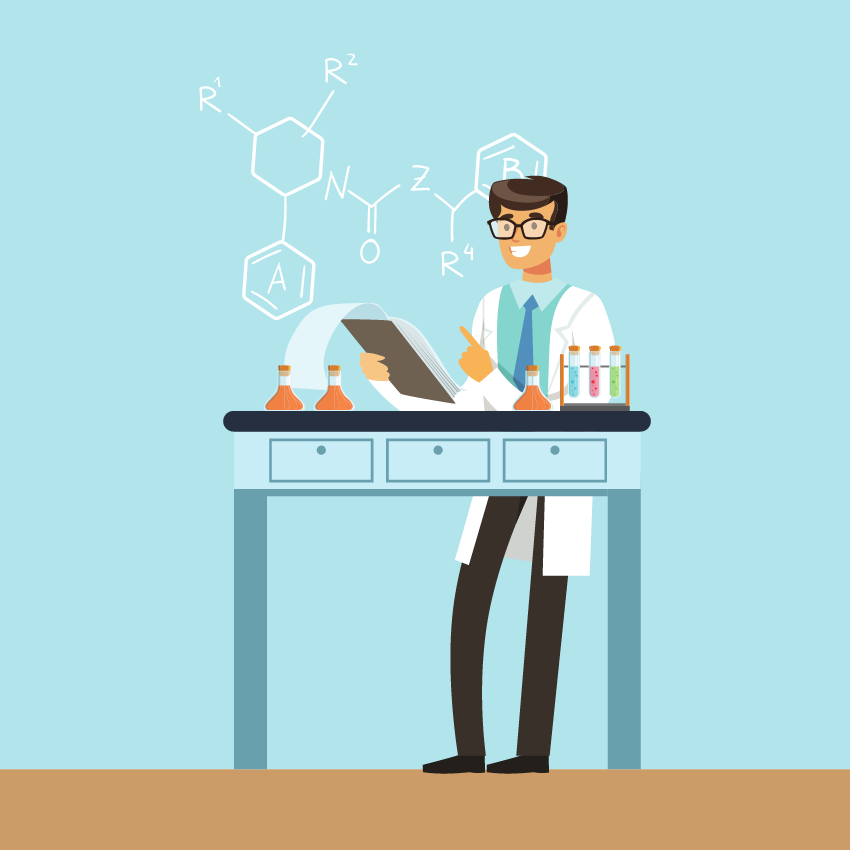
医薬品候補の化合物を飲み薬である錠剤や注射剤など、実際に投与できる形に製剤設計する部署です。
大学では製剤の研究室は薬学部にしかないですが、製薬企業では製剤設計、治験薬製造、工場への製剤の移管など業務は多岐に渡ります。
まとめ
研究部門の主な部署について紹介しました。
- 合成部門
- 薬理部門
- 分析部門
- 安全性部門
- 薬物動態部門
- 製剤部門