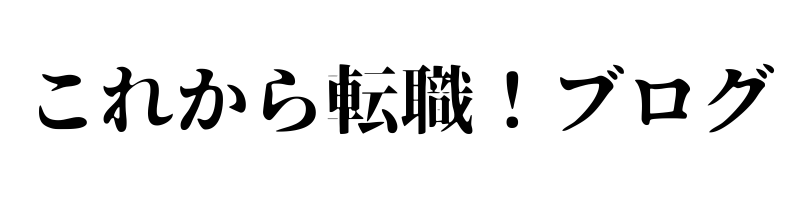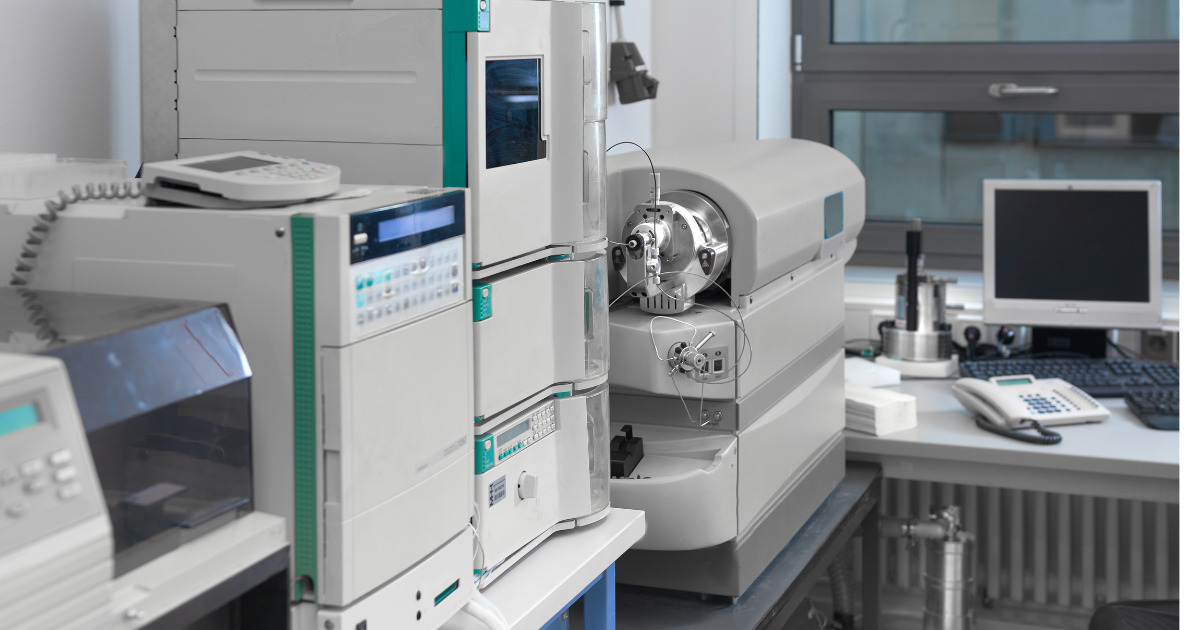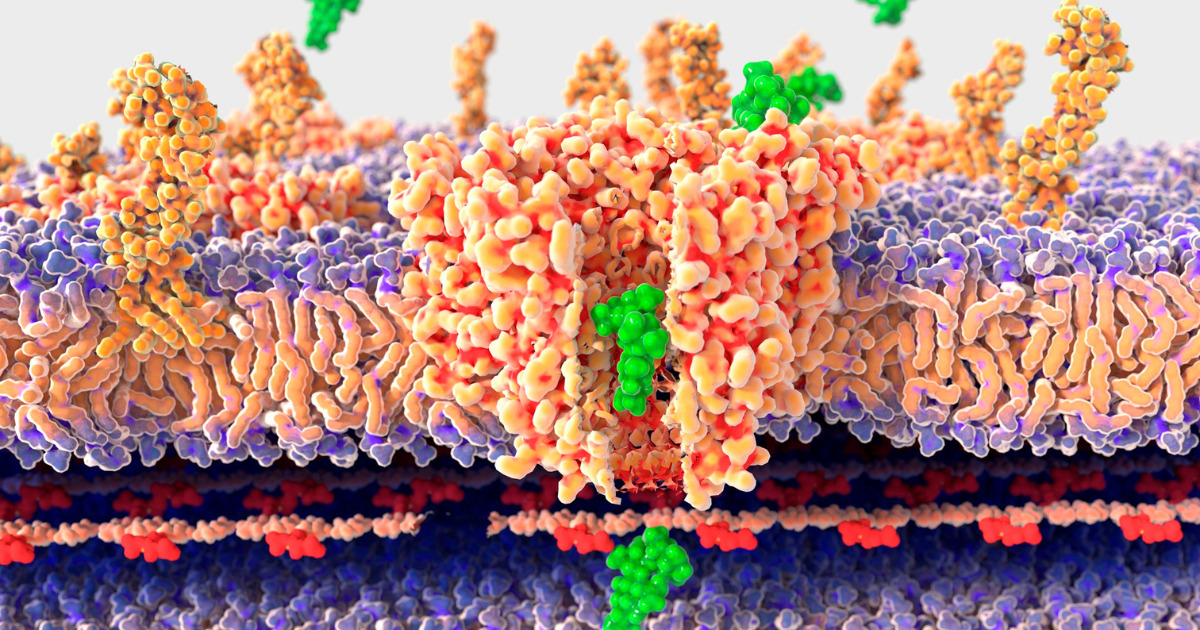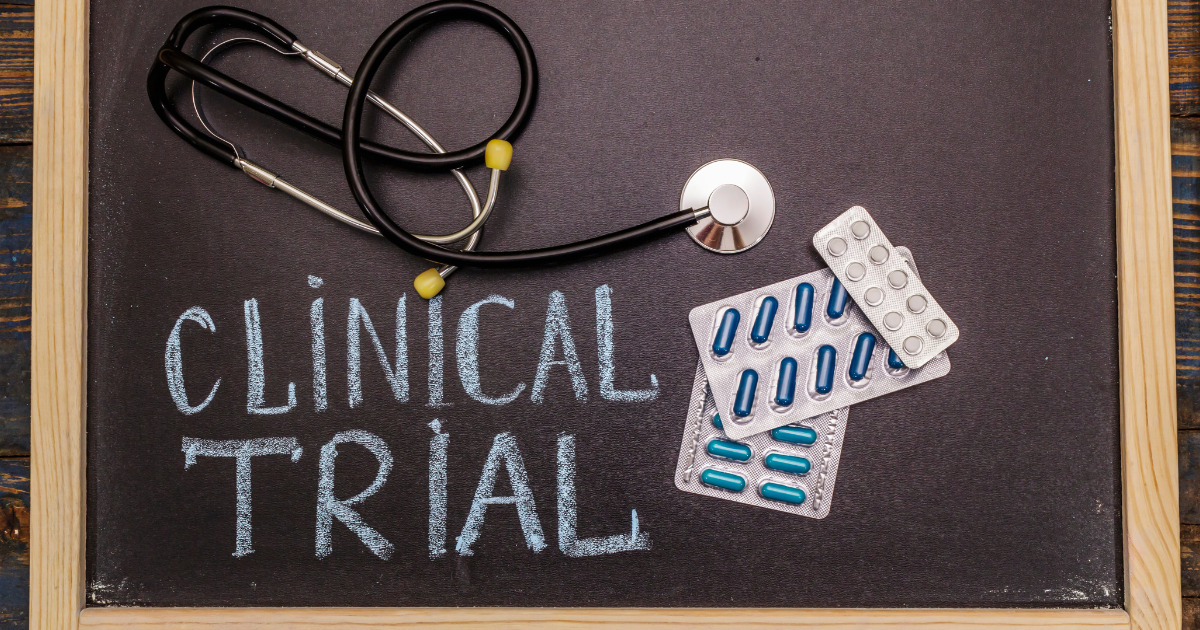製薬企業の研究部門の中で、医薬品となる化合物を製造(合成)する合成部門について紹介します。
目次
有機合成を実施
合成部門は有機合成を主に実施します。
有機合成とは簡単にいうと、炭素の周りに官能基を修飾したり、炭素を有する有機化合物同士を結合したり(CーC結合)して、目的とする化合物、製薬企業の場合は医薬品候補化合物を作成します。
低分子とは分子量1000程度までです。
仕事の種類:創薬合成とプロセス合成
合成部門の仕事は大まかに創薬合成とプロセス合成に分かれます。
創薬合成
創薬合成は薬理部門と協力して目標(ターゲット:受容体など)に最適な化合物の候補を見つけます。
プロセス合成
創薬合成で得られた化合物の合成経路の最適化を実施するのがプロセス合成です。
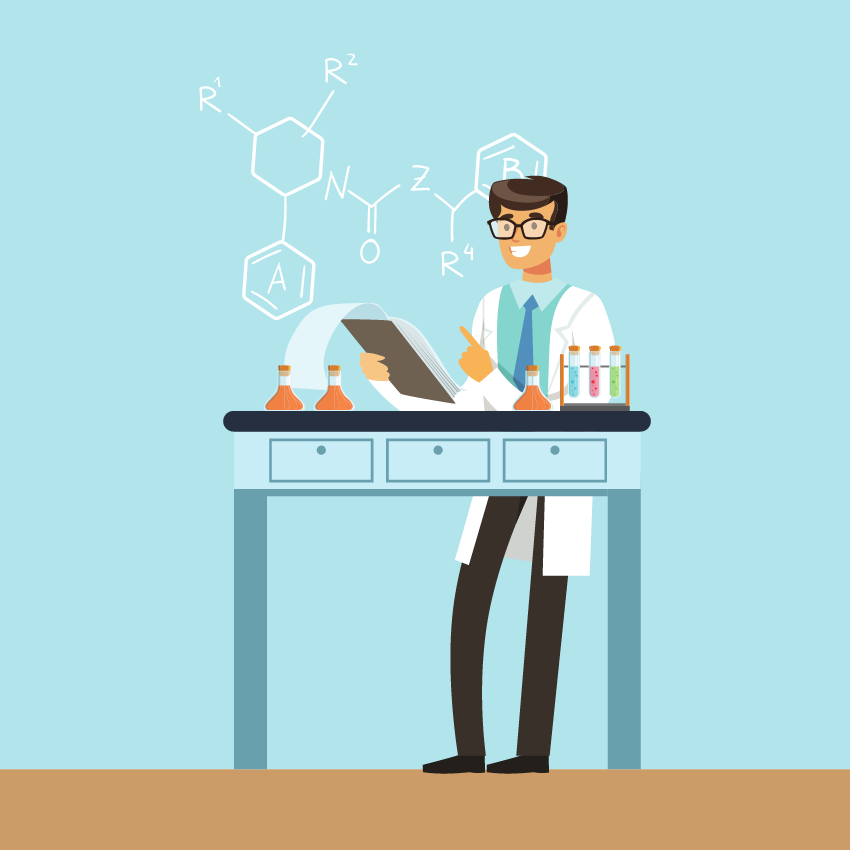
その際スケールアップも担当します。
スケールアップでは原薬工場に合成を委託するため、日本だけでなく、海外の工場へも行くことになります。
合成部門の特徴:専門性が高い
有機合成のところで記載したように、合成を行うには修飾や結合を駆使して化合物を設計(デザイン)する必要があります。
具体的には大学の合成に関わる研究室、例えば薬学部の合成研究室、理学部の化学研究室、農学部の農芸化学の研究室、工学部の工業化学研究室などで勉強する必要があります。
これらの研究室で大学院まで進学して勉強したもののみが、製薬企業の合成部門に配属されます。
製薬企業の研究部門として
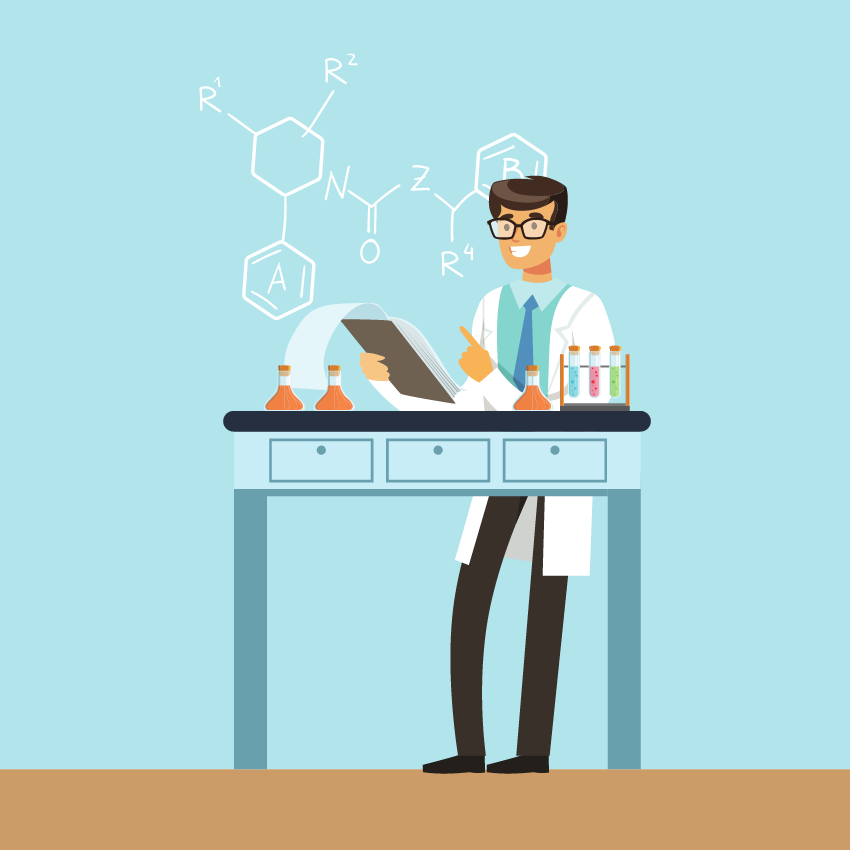
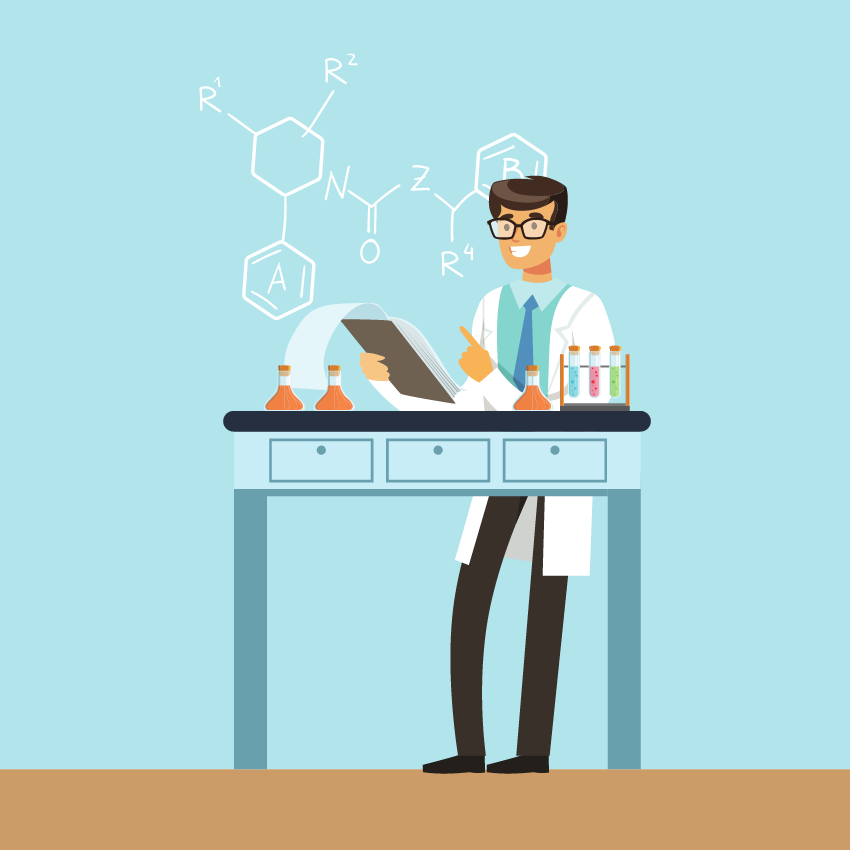
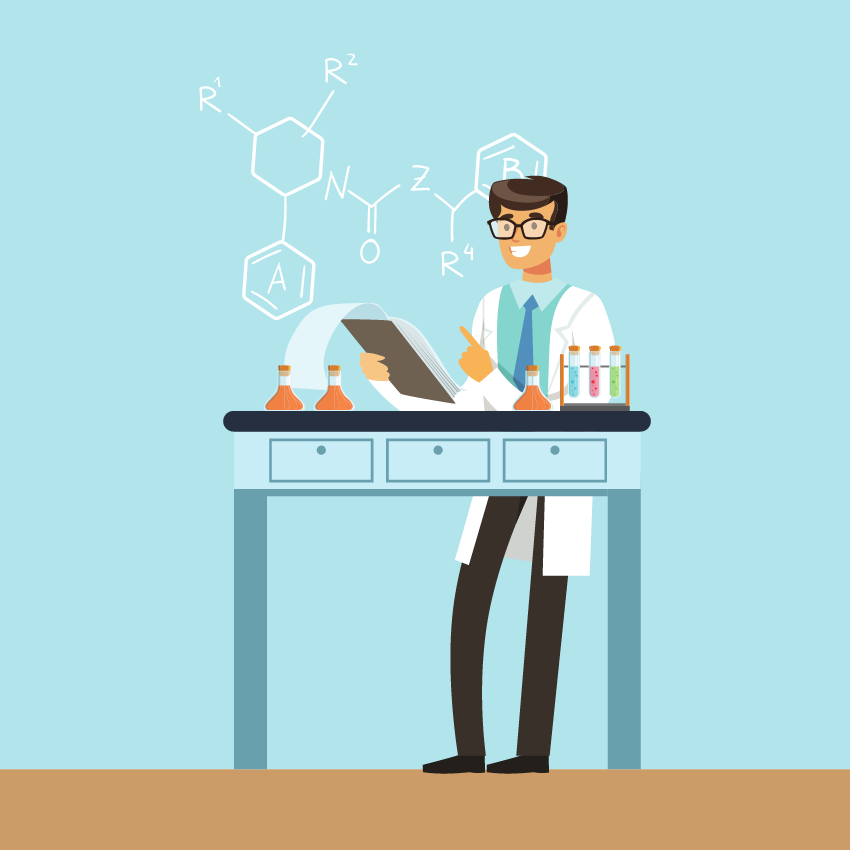
合成部門は長らく研究部門の花形(人もお金も多い)の一つです。
医薬品の候補となる化合物そのものを合成するので、化合物特許も作成します。
最近では医薬品が高分子であることも多いため、合成部門ではなく薬理部門など他の部門が中心となることもあります。
それでも低分子の医薬品もまだまだ多いため、活躍が期待されます。
まとめ
製薬企業の研究部門の中で、合成部門について紹介しました。
- 有機合成を実施
- 仕事の種類:創薬合成とプロセス合成
- 合成部門の特徴:専門性が高い
- 製薬企業の研究部門として